
ジェンダーギャップ、どう感じてる?ー理系で学ぶ学生たちの声
近年、理系を学ぶ女子学生、いわゆる「リケジョ」を支援するコミュニティやイベントの存在を耳にする機会が増えました。少しずつ女性の進出は進んでいるものの、理系分野におけるジェンダーギャップは依然として大きな課題として残っています。
今回は、筆者の周囲にいる理系を専攻する大学生・大学院生・教授・社会人の方々にアンケートを実施し、その実情に迫りました。
自己紹介:筆者は中学校から女子校に通い、現在はアメリカの大学で化学を専攻しています。STEM分野での女性支援活動として「Go STEM」のアンバサダーとしても活動中です。
数字で見るジェンダーギャップ
まず、日本における理系分野の男女比のデータを見てみましょう。
理系分野に就いている女性は16%にとどまっており、この数字はOECD諸国の中でも最も低い水準です。
ちなみに筆者が学ぶアメリカでも、ジェンダーギャップは依然として大きく、特に物理学や工学などの分野では、女性の進出が遅れているのが現状です。
実際の声:理系分野で感じるジェンダーギャップ
筆者が実施したアンケートには、大学生・大学院生・社会人・教授の計22名が回答してくれました。まず、「理系分野で男女の格差を感じたことがありますか?」という質問には、15名(約70%)が「はい」と回答。
差別や偏見を感じた場面としては、「学校」が最も多く、次いで「職場」や「クラブ・サークル活動」などが挙げられました。
一方で、「わからない」と答えた方も7名いました。理由としては、「まだ基礎科目しか受講しておらず、女子学生の方が多いクラスもあるため、実感がない」という声がありました。
なぜジェンダーギャップは埋まらないのか
次に、「なぜジェンダーギャップが生じていると思うか」という質問をしたところ、最も多かったのは
「理系=男性向け」という偏見でした。
実際には、男女の脳の能力差は科学的に証明されていないにもかかわらず、日本・アメリカともにこのような固定観念が依然として根強く残っています。
次いで多かったのは、女性のロールモデルが少ないことです。
「自分と似た背景を持つロールモデルの存在」は、進路選択において大きな影響を与える要素です。憧れる先輩や身近な成功例がないことで、理系の道に進む決断が難しくなることもあります。
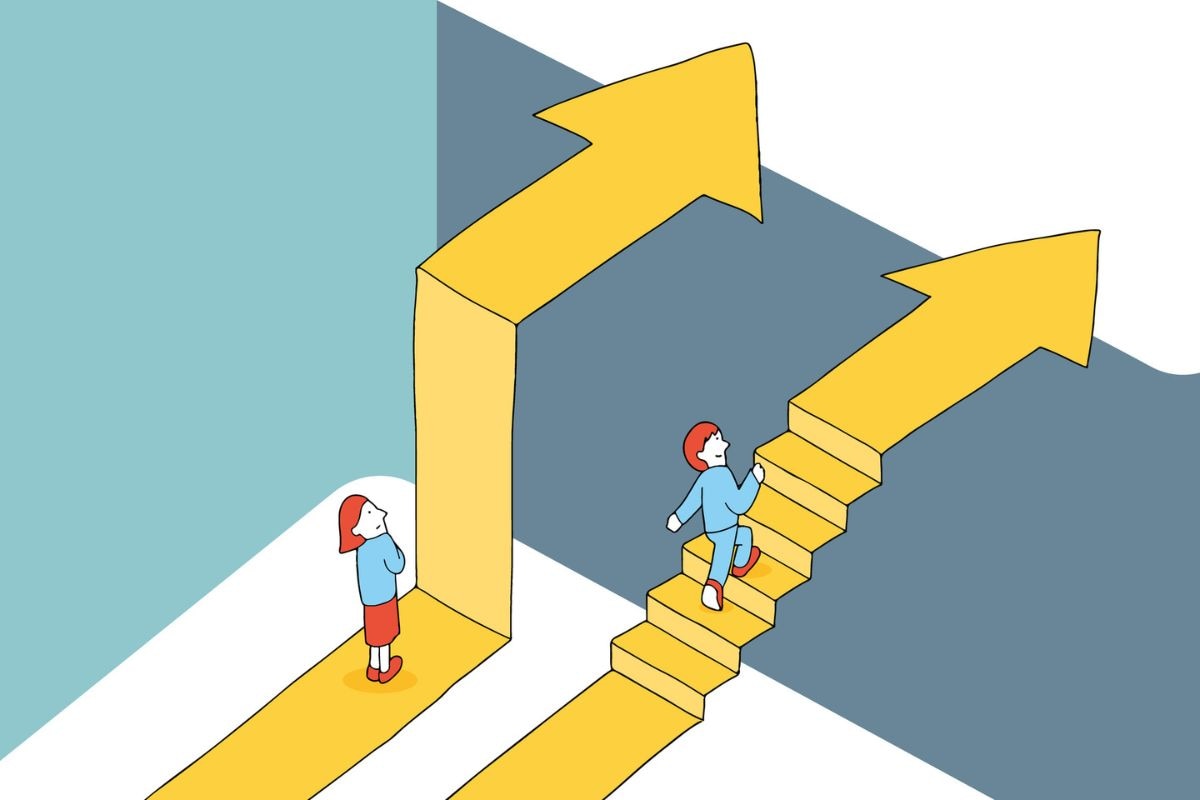
増え始めたリケジョ支援の取り組み
現在、日本でも海外でも、ジェンダーギャップ解消に向けた取り組みが活発化しています。
女子向けの科学キャンプ、理系で活躍する女性との座談会、メンタープログラムなど、支援の場は多様化しています。
中でも筆者が注目しているのが、「山田進太郎D&I財団」の奨学金プロジェクトです。 これは、理系進学を目指す中高生を対象にした返済不要の奨学金で、文理選択という重要なタイミングで理系進路を後押しする、非常に効果的な支援です。
アメリカでは、大学入学後に専攻を自由に変更できる仕組みがあるため、進路変更も比較的柔軟です。実際、筆者の友人にも、入学後に興味が変わり、文系から理系に転向した学生が多くいます。
一方で日本では、中高生の段階で文理選択を迫られるため、その後の進路変更が難しい傾向があります。このことからも、中高生への早期アプローチが極めて重要だと言えるでしょう。
まとめ
今回は、理系分野で学び働く人々のリアルな声を通して、ジェンダーギャップの現状とその背景、そして解決への取り組みを紹介しました。
理系に進もうか迷っている方、あるいは身近にそのような方がいる場合は、ぜひ一度イベントや支援プログラムに参加してみてください。
まだまだ「リケジョ」はマイノリティかもしれませんが、少しずつ環境は変わってきています。ジェンダーギャップが解消され、誰もが自由に進路を選べる未来が近づいていると信じています。










